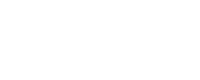作詞:外山正一
作曲:シャルル・ルルー
1.
吾(われ)は官軍我が敵は 天地容れざる朝敵ぞ
敵の大将たる者は 古今無双の英雄で
これに従うつわものは 共に慄悍決死(ひょうかんけっし)の士
鬼神に恥じぬ勇あるも 天の許さぬ反逆を
起こせし者は昔より 栄えしためしあらざるぞ
敵の亡ぶるそれ迄は 進めや進め諸共に
玉散る剣抜きつれて 死する覚悟で進むべし
吾(われ)は官軍我が敵は 天地容れざる朝敵ぞ
敵の大将たる者は 古今無双の英雄で
これに従うつわものは 共に慄悍決死(ひょうかんけっし)の士
鬼神に恥じぬ勇あるも 天の許さぬ反逆を
起こせし者は昔より 栄えしためしあらざるぞ
敵の亡ぶるそれ迄は 進めや進め諸共に
玉散る剣抜きつれて 死する覚悟で進むべし
2.
皇国(みくに)の風(ふう)ともののふは その身を護る魂の
維新このかた廃れたる 日本刀(やまとがたな)の今更に
また世に出ずる身のほまれ 敵も味方も諸共に
刃(やいば)の下に死ぬべきぞ 大和魂あるものの
死すべき時は今なるぞ 人に後(おく)れて恥かくな
敵の亡ぶるそれ迄は 進めや進め諸共に
玉散る剣抜きつれて 死する覚悟で進むべし
皇国(みくに)の風(ふう)ともののふは その身を護る魂の
維新このかた廃れたる 日本刀(やまとがたな)の今更に
また世に出ずる身のほまれ 敵も味方も諸共に
刃(やいば)の下に死ぬべきぞ 大和魂あるものの
死すべき時は今なるぞ 人に後(おく)れて恥かくな
敵の亡ぶるそれ迄は 進めや進め諸共に
玉散る剣抜きつれて 死する覚悟で進むべし
3.
前を望めば剣なり 右も左もみな剣
剣の山に登らんは 未来のことと聞きつるに
この世において目(ま)のあたり 剣の山に登らんは
我が身のなせる罪業(ざいごう)を 滅ぼすために非ずして
賊を征伐するがため 剣の山もなんのその
敵の亡ぶるそれ迄は 進めや進め諸共に
玉散る剣抜きつれて 死する覚悟で進むべし
前を望めば剣なり 右も左もみな剣
剣の山に登らんは 未来のことと聞きつるに
この世において目(ま)のあたり 剣の山に登らんは
我が身のなせる罪業(ざいごう)を 滅ぼすために非ずして
賊を征伐するがため 剣の山もなんのその
敵の亡ぶるそれ迄は 進めや進め諸共に
玉散る剣抜きつれて 死する覚悟で進むべし
4.
剣の光ひらめくは 雲間に見ゆる稲妻か
四方(よも)に打ち出す砲声は 天にとどろく雷(いかずち)か
敵の刃に伏す者や 弾に砕けて玉の緒の
絶えて果敢(はか)なく失(う)する身の 屍(かばね)は積みて山をなし
その血は流れて川をなす 死地に入るのも君のため
敵の亡ぶるそれ迄は 進めや進め諸共に
玉散る剣抜きつれて 死する覚悟で進むべし
剣の光ひらめくは 雲間に見ゆる稲妻か
四方(よも)に打ち出す砲声は 天にとどろく雷(いかずち)か
敵の刃に伏す者や 弾に砕けて玉の緒の
絶えて果敢(はか)なく失(う)する身の 屍(かばね)は積みて山をなし
その血は流れて川をなす 死地に入るのも君のため
敵の亡ぶるそれ迄は 進めや進め諸共に
玉散る剣抜きつれて 死する覚悟で進むべし
5.
弾丸雨飛(うひ)の間にも 二つなき身を惜しまずに
進む我が身は野嵐に 吹かれて消ゆる白露の
果敢(はか)なき最期を遂ぐるとも 忠義のために死する身の
死して甲斐あるものなれば 死ぬるも更にうらみなし
われと思わん人たちは 一歩もあとへ引くなかれ
敵の亡ぶるそれ迄は 進めや進め諸共に
玉散る剣抜きつれて 死する覚悟で進むべし
弾丸雨飛(うひ)の間にも 二つなき身を惜しまずに
進む我が身は野嵐に 吹かれて消ゆる白露の
果敢(はか)なき最期を遂ぐるとも 忠義のために死する身の
死して甲斐あるものなれば 死ぬるも更にうらみなし
われと思わん人たちは 一歩もあとへ引くなかれ
敵の亡ぶるそれ迄は 進めや進め諸共に
玉散る剣抜きつれて 死する覚悟で進むべし
6.
吾(われ)今ここに死なん身は 国のためなり君のため
捨つべきものは命なり たとえ屍は朽ちるとも
忠義のために死する身の 名は芳しく後の世に
永く伝えて残るらん 武士と生まれし甲斐もなく
義のなき犬と言わるるな 卑怯者とな謗(そし)られそ
敵の亡ぶるそれ迄は 進めや進め諸共に
玉散る剣抜きつれて 死する覚悟で進むべし
吾(われ)今ここに死なん身は 国のためなり君のため
捨つべきものは命なり たとえ屍は朽ちるとも
忠義のために死する身の 名は芳しく後の世に
永く伝えて残るらん 武士と生まれし甲斐もなく
義のなき犬と言わるるな 卑怯者とな謗(そし)られそ
敵の亡ぶるそれ迄は 進めや進め諸共に
玉散る剣抜きつれて 死する覚悟で進むべし
さて、抜刀隊とは一体なんでしょうな。
時は1877年(明治10年)熊本、勝敗の分水嶺となった西南戦争最大の激戦地「田原坂(たばるざか)の戦い」において、川路利良(かわじ としよし)が率いる警視隊から組織された別働第三旅団から選抜して臨時に編成され投入された白兵戦部隊のことなんです。
田原坂(たばるざか)は、長さ1,500m、標高差60mのゆるやかな坂。熊本城を目指す官軍小倉連隊と薩軍が、3月4日から17昼夜も一進一退を繰り返した、西南戦争最大の激戦地である。
ここは高瀬から熊本へ大砲を運ぶ唯一のルート。薩軍は多数の塁を築き濠を巡らして、官軍を待った。しかも街道は丘陵の腹をえぐるように蛇行曲線を描いた凹道で、下から攻め登ろうとする官軍は前方の見通しが効かず、容易に進むことができなかった。実はここも清正公が、北の備えとして築いた拠点だったのである。
薩軍は薩摩示現流(じげんりゅう)の激烈な必殺剣で斬り込む。対する官軍は狙撃兵を配して、これを撃つ。しかし、官軍は、一の坂・二の坂・三の坂と3つに分かれる田原坂(たばるざか)の最後のたった300mを越えることができなかった。降り続ける雨の中、1日32万発もの銃弾の雨が飛び交い、弾同士が空中で激突し潰れた残骸が今でも残されている。
雨は降る降る、人馬は濡れる、越すに越されぬ田原坂
そんな激戦も永遠に続くことはない。3月20日、とうとう田原坂(たばるざか)は陥ちた。帝国陸軍は西郷隆盛(薩軍)の手から田原坂を奪取し、進軍の突破口を開いた。
※私は間違えて”たばらざか”と読んでしまっております。正式には”たばるざか”です。情報を頂きありがとうございます。