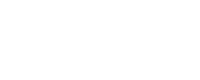月日は永遠の旅人であり、来ては過ぎる年もまた旅人のようなものである。絶えることなく行き交う舟の上に人生を浮かべる船頭、馬の口をつかまえて老境を迎える馬方などは、毎日が旅であり旅を自らの住処としている。昔の人も旅の途上で死んだ者は多い。私もいつの頃からだろうか、千切れ雲が吹き飛ばされる風情に誘われて、さすらいの旅に出たい気持ちを抑えられず、須磨・明石など近くの海辺をさすらったりしていた。去年の秋、ようやく隅田川のほとりにある深川芭蕉庵の家に戻り、古巣を払いのけたりなどしている内にその年も暮れた。
春の空に霞が立ちこめるようになると、白河の関を越えたいと思い、そぞろ神のせいか、気持ちが妙にそわそわして狂おしい心境になり、道祖神の招きにもあって取るものも手に付かなくなってしまった。旅の準備をするために、股引きの破れを直して、笠の紐をつけかけ、足を丈夫にする三里のツボにお灸を据えたが、まずは松島の月の風情が心に浮かんできて抑えられない。今の小さな庵は人に譲って、弟子の杉風(さんぷう)の別荘にまずは移った。
草の戸も 住み替はる代ぞ 雛の家
え?意味が分からない?
分かりやすく説明しましょうかな。
私の庵は小さな草の戸で出来た質素な庵でございます。
いよいよこの質素な家も、主が変わる時だなぁ。
どんな新しい住人が住むか分からないが、その新しい住人は、女の子の子供もいて、ひな人形を飾ったりもするのだろうか。
そんな思いを詠んだんですな。
この最初の句を書き付けた表八句の紙を庵の柱に掛け置いて、旅立つ前の挨拶とした。