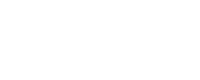99代後光厳天皇(ごこうごんてんのう)の治める時代。
貞治(じょうじ)4年9月、足利将軍義詮(よしのり)公が病気によりその政務を義満(よしみつ)公に譲った。
また同じ年に、鎌倉の管領左馬頭基氏(さまのかみもとうじ)が逝去した。
左馬頭基氏(さまのかみもとうじ)の息子、氏満(うじみつ)が続いて管領職を引き継ぎ、執事憲顕(のりあき)がこれを補佐し、関東の面々はことごとく氏満(うじみつ)の武徳にひれ伏した。
時を同じくして、信濃国の主護職小串次郎左衛門尉貞行(こぐしじろうざえもんのじょうさだゆき)の家臣に唐琴浦右衛門(からことうらうえもん)という忠義に厚い侍がいた。
浦右衛門は、主である小串の館より半里ほど離れたところにある筑摩川(千曲川ちくまがわ)の畔に居宅をかまえておった。
浦右衛門には桟(かけはし)という10年連れ添った三十路を越えた妻がおり、夫婦大変仲睦まじい関係であった。
しかしながら、この夫婦は子宝に恵まれず、初老に差し掛かった浦右衛門はこれを大いに愁いておった。
世継ぎの欲しい浦右衛門は、神仏に祈り続けるも果報はなく、桟(かけはし)の妊娠の兆候もない。
その頃、絶海という禅僧と共に大明(たいみん)に渡った、泉州堺の浪人粟野十郎左衛門(あわのじゅうろうざえもん)が帰朝の際に、金魚両尾を持ち帰った。
これが金魚という魚が日本にやってきた始まりである。
浦右衛門は職務で上京した際に、この金魚という魚が大明より伝来したことを聞きつけ、珍品を好む主人の次郎左衛門(じろうざえもん)に贈れば喜ぶだろうと思いたった。
早速浦右衛門は家来を堺にある、かの粟野の居宅へ遣わし、小判20両にて雌雄両尾の金魚を入手した。
その後、国に帰り主人の次郎左衛門(じろうざえもん)に献上したところ、次郎左衛門(じろうざえもん)は、「なんと美しい魚であるか」と大喜びし、その褒美として浦右衛門がかねてより大層欲しがっていた鎬藤四郎(しのぎとうしろう)の刀を賜った。
次郎左衛門(じろうざえもん)は、水槽を造りこの金魚を大切に育てると、次第に子を成しその数が増えて行った。
大明の医師、李時珍(りじちん)が著した本草綱目(ほんぞうこうもく)によると、金魚は宋(そう)の時代に初めて飼う者があったという。
唐土(中国)では金魚を飼うという行為はずいぶんと長く続いているようだ。
抱朴子(ほうぼくし)によると、上洛県(じょうらくけん)冡嶺山(ちょれいさん)に丹水があり、丹魚(たんぎょ)が棲んでいるとあるが、これも金魚の種類のひとつであろう。
中国人は金魚をこよなく愛しており、陳淏子(ちんこうし)が花鏡にその育て方を詳しく記録している。
さて、次郎左衛門(じろうざえもん)の金魚は益々増え続けた。
次郎左衛門(じろうざえもん)は浦右衛門にも「お前も育てよ」とこれらを分け与えた。
浦右衛門はこれを大切に大切に育て、この金魚も子を成し数を増やしていった。
この金魚、その身は赤白(しゃくびゃく)の斑紋があり、尾鰭は金色に照りわたり、まさに紅葉が散り竜田川に流れ、からくれないに水くくる風情があった。
これを見た者たちは、それはそれは感心したものだ。