室の八島明神に参拝した。このとき旅の連れ合いの曽良は、こう語った。『この神社に祭ってある神は、古事記に登場する木花咲耶姫(このはなさくやひめ)と申しまして、富士山麓にある浅間神社と同じ神なのです。
この姫はわずか一夜で妊娠して、夫のニニギノミコトに貞節を疑われた時、自分の子どもが夫の子であることを証明するため、自らの閉じた部屋に火を放ちましたが、子が焼け死ななかったことでニニギノミコトの子であることが明らかになりました。この彦火火出見の尊(ひこほほでみのみこと)という子どもが生まれたことで、竈のように燃える姫の室という意味を込めて、室の八島と呼ばれるようになったのです。室の八島には煙にちなんだ歌を詠む習わしがありますが、それも木花咲耶姫の逸話に基づくものです。』
また、この地方では「このしろ」という魚を食べるのを禁じている。このしろを禁じている縁起は、このしろを焼く匂いが、木花咲耶姫のエピソードと関連して人体を焼く匂いに変わるというものだが、このように世間に伝えられている話は多い。
3月30日は、日光山の麓に泊まった。宿の主人が、『私の名前は仏五左衛門です。何事にも正直であることを旨としていますので、人が私のことをそう呼んでいます。ですから、今晩のご宿泊も安心してくつろいで泊まっていって下さい。』と言ってきた。どのような仏が、濁り汚れた俗世に出現してきたのか、こんな僧形をした乞食巡礼みたいな私たちを助けてくれるのかと、主人の振る舞いや態度を集中して観察してみた。
その宿の主人は、余計な悪知恵を持っておらず物事を選び分けるような分別も無い、正直であることだけにひたすら偏っている人物であった。意志堅固で虚飾がなく素朴な人柄は、儒教でいう『仁徳・人格者』の類に近い。こういった邪心のない心清らかな朴訥な性格は尊ばなければならない。
4月1日、日光山に参拝した。昔はこの山を『二荒山』と書いたんですが、真言宗の開祖・空海弘法大師がここに寺社を建立した時、『日光』と改名したんですな。
千年後の未来の繁栄を予見されていたのか、今や徳川幕府の権威をも反映してこの日光山の威光は国中に輝いており、その恩恵は国中に溢れている。士農工商の市民はみな平穏な生活を送ることができ天下も安泰である。これ以上、日光山について書くのは畏れ多いことなので、筆を置くことにする。
あらたふと 青葉若葉の 日の光
え?意味がわからない?
では、わかりやすいように現代語でお話ししましょうかな。
「なんということでしょう!尊くありがいことだ。ここ日光の山の木々の青葉や若葉に降り注ぐ日の光は。まさに東照宮や幕府の威光を浴びて輝いているようだ。」

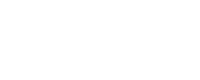
「【現代語訳】おくのほそ道 #4 ~室の八島明神・日光山~ 【松尾芭蕉】」への1件のフィードバック