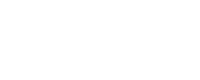大名の奧方の病が重くなつて危篤にせまつてゐた、そして奧方は自分でも危篤にせまつて居る事を承知してゐた。文政十年の秋の始めから床を離れる事はできなかつた。今は文政十二年――西洋の數へ方では一八二九年――の四月であつた。櫻の花が開いてゐた。彼女は庭の櫻の花と陽氣な春の事を考へた。彼女は子供の事を考へた。彼女は夫の色々の側室の事――殊に十九歲の雪子の事を考へた。
大名は云つた、『わが妻、この三年の長い間の御身の病氣、さぞ苦しかつたであらう。御身を直すために、――夜晝御身の側で看護をなし、御身のために祈り、又御身のために斷食までもして――あらん限りをつくして居る。しかしその心づくしのかひもなく、最も良い醫師達の配劑のかひもなく、御身の命脈も今甚だ心細くなつて居る。御身が佛の云はれたこの三界の火宅を去つて行かれる事は御身よりも自分等の方がどれ程悲しいか分らない。自分は御身の後生の冥福を祈るために、どんな佛事をも――費用を惜まず――行ひます、又自分等は御身の魂の中有に迷はず、直ちに極樂淨土に赴いて佛果を得るやうにたえず祈ります』
彼はその間彼女を撫でさすりながら、この上もなくやさしく云つた。その時、眼を閉ぢたままで、彼女は蟲のやうな細い聲で、彼に答へた、――
『御親切なお言葉――有難うございます――本當に有難うございます。……はい、全く仰せの通り、私三年の長い間病氣でした、そしてこの上もない御世話と御親切に預かりました。……この最期に臨んで何の迷をいたしませう。……今となつて浮世の事に心を殘すのもまちがひかも分りませんが、――私一つ、たつた一つ、御願がございます。……ここへあの雪子を呼んで下さい、――御承知の通り私雪子を妹のやうに可愛がつて居ります。私あとあとの事色々話して置きたうございます』
雪子は大名の命によつてそこへ現れた、それから彼からの合圖に從つて、床の側に跪いた。奧方は眼を開いて、雪子を見て、云つた、――
『あ〻雪子か。……よく來てくれたね。……私は大きな聲が出ないから、よく聞えるやうに――もう少し近くへ進んでおくれ。……雪子、私もう死にます。そなたはこれから、あの殿樣を萬事につけて御大切に御世話を申上げて、――私の亡きあとには私の代りになつて貰ひたい。……そしていつまでも御寵愛を受けて、――さうです、私の百倍も御寵愛を受けて、――やがて昇進して奧方におなりなさいよ。……そしていつでも殿樣を大事にして他人に寵を奪はれないやうになさいよ。……雪子さん、これが御身に云ひたかつた事です。……分りましたか』
『あゝ、それは又物體ない御言葉。御存じのやうな私風情の貧しい賤しい生れの者が、――奧方にならうなどとはとんでもない事でございます』雪子は抗言した。
『いや、いや、今遠慮や他人行儀を云つて居る時ではない、お互に本當の事だけを云ひませう』奧方はかすれた聲で答へた。『私が死んだら、そなたは必ずよい地位に昇進するであらう、そして今又たしかに云うて置くが、私はそなたが奧方になるやうにと願つて居ります、――さうです、私が成佛する事よりもこの事をもつと願つて居ります。……あ〻、忘れようとしてゐた、――雪子、私の願を一つ聞入れておくれ。そなたの知つての通り、庭に一昨年、大和の吉野山から取寄せた八重櫻があります。それが今滿開であると聞いて居る、――それで私その花を見たい。もうぢきに私は死ぬが、――死ぬ前にその花を見たい。私を庭へ、――雪子、すぐに、――その花の見えるやうに連れて行つて貰ひたい。……さあ、背中に、雪子、――おぶつておくれ。……』
かう云つて居るうちに、彼女の聲は段々はつきり强くなつて來た、――丁度その願の强さのために新しい力が出て來たやうであつた、それから不意に彼女は泣き出した。雪子はどうしてよいか分らないから、動かないで跪いてゐた、しかし大名は承諾の意味の合圖をした。
彼は云つた、『これはこの世の最後の願だ。彼女はいつでも櫻の花が好きであつた、それでその吉野の花をさぞ見たいだらうと察する。さあ雪子、望み通りに致してやれよ』
子供にとりつかせるために、乳母が背中を向けるやうに、雪子は奧方に彼女の肩を向けて云つた、――
『用意を致して居りますから、どう致してよいか御指圖を遊ばして下さい』
『あゝ、こちらへ』――瀕死の女は答へて、殆ど超人間的努力で立上つて雪子の肩にしがみついた。しかし雪子が立つた時、彼女は頸筋から、着物の下へ、彼の細い手をすばやく差し込んで、この少女の乳房をつかんで、物すごい笑を高く上げた。
『思ひが叶つた』彼女が叫んだ――『私は櫻の花に心が殘つた、――庭の櫻の花ではない。……私の願の叶ふまでは死にきれなかつた。今それが叶つた、――あゝ嬉しい』
それからさう云つたまま、蹲(うづくま)つて居る少女に倒れかかつて、息は絕えた。
侍者達は直ちに雪子の肩から、その死體を取つて床の上に置かうとした。ところが――不思議にも――この見たところ何でもない事ができなかつた。その冷い手が少女の乳房に何か說明のできないやうな風に固着してゐた、――その生きた肉となつてしまつたやうに見えた。雪子は恐怖と苦痛のために知覺を失つた。
醫者は呼ばれた。彼等にはどうなつたのか合點が行かなかつた。普通の手段では、死んだ人の手は彼女の犧牲の肉體から離す事ができなかつた、――離さうとすると血が出る程に固着してゐた。これは指がつかんで居るからではなかつた、それは掌の肉が乳房の肉と說明のできないやうに結合してゐたからであつた。
その當時、江戶の最も熟練なる醫者は外國人――オランダの外科醫――であつた。その人を呼ぶ事にきまつた。丁寧に調べたあとで、彼はこんな患者の例は知らないと云つた、それから雪子を直ちに救ふためには、死體から兩手を切斷するより外に方法はないと云つた。乳房から手を離さうとする事は危險であると斷言した。その忠告は用ひられて、兩手は手首から切斷された。しかし手は乳房に固着したままになつた、やがてそこで黑くなつてしなびた、――長く死んだ人の手のやうに。
しかしこれは恐ろしさのただ始まりであつた。
しなびて血のないやうに見えてゐながら、その手は死んでゐなかつた。時々――そつと、大きな灰色の蜘蛛のやうに――動き出す。そしてそれから每晚――いつでも丑の刻から――つかんで、締めて、責め始める。寅の刻になつてやうやくその苦痛が止む。
雪子は剃髮して巡禮の尼になつて、脫雪と名を改めた。彼女は彼の亡くなつた奧方の戒名、――妙香院殿知山涼風大姊、――のある位牌を造らせて、每日その前に赦しを願つて、その嫉妬の心の止むやうに囘向した。しかしこんな苦痛の源となつて居る因果は中々に消滅はしなかつた。每晚丑の刻になると、その手はきまつて彼女に責苦を與ヘた、――彼女が下野の國河內郡田中村の野口傳五左衞門と云ふ人の家に泊つた時、最後にこの話を聞いた人達の證言によれば、――それがもう十七年以上にもなる。それが弘化三年(一八四六年)であつた。
この尼のその後の話は分らない。