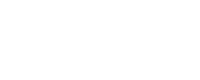ひと目惚れは日本では西洋ほどありふれたものではない。一つには東洋社会の特有の構造のためであり、もう一つには恋愛にまつわる多くの不幸は親が取決める早婚によって未然に防がれているからである。しかし他方で、情死がしばしば起っているが、そこにはほとんどつねに二人一緒になされているという特徴がある。これらの多くの場合は不適切な関係つまり道ならぬ恋の結末であるといえよう。とはいっても誠実かつ勇気ある例外の場合もまた存する。こちらは大概は田舎の方で起きている。このタイプの悲劇における恋愛は、少年少女の無垢で自然な友情からにわかに進展したものであり、また犠牲者たちの幼少の時期にまで遡ることができる。ところで、西欧での恋人同士の自殺と日本の情死との間には、とても意義深い違いがある。東洋の心中は苦しみに耐えきれず、衝動的で突発的な狂乱の結果ではない。むしろそれは冷静でありまた秩序だったものである。加えて、それは神聖なる儀式でもある。言い換えると心中は自らの死をもって証とする婚礼という意味合いを持っている。二人の誓約は神の前でなされ、それぞれ遺書を認めて、そして死に行くのである。これほどに意義深く聖なる誓いはあるまい。それだから、外部から妨げられたりあるいは治療を施されたりして、二人のうちの一人が死から救い出され生き残るようなことになれば、死に損なった者はこの愛と名誉の神聖なる誓約に基づいて、できるだけ速やかに命を捧げるべきであるとされている。相手に対して人としての正しい筋道を通す義理があるからである。もちろん、二人がともに救い出された場合はさほど問題はない。しかし、若い女性と一緒に死ぬことを誓った後に冥土への旅を娘一人にさせた男として記憶されるよりは、刑務所に五〇年ばかり投獄されるような罪を犯した方がよほどましである。誓いを破った女の方はまだしも赦されもする。けれど、情死を邪魔立されて未遂となった男が一度きり不首尾に終わったからといって恥知らずにものうのうと生き残ろうものならば、大嘘つきや人殺し、腰抜けの臆病者それに人の顔をした畜生などと蔑まれて残りの人生を送るのが関の山であろう。私はそのような例を一つ知っている――が、ここでは東国のある村で起こった純朴な恋の物語をすることにしたい。
1
その村は、幅の広い川のほとりにあるが、川は浅く梅雨時になってやっと川床が隠れるほどである。また北から南へと流れていて周囲に広がる広大な水田を潤している。西の方には山々の青い峰が連なっており、東の方には低い森の丘陵が伸びている。丘陵と村の間には八〇〇メートルほどの幅の水田が広がっていた。村の主な墓地は丘の上にあり、十一面観音を本尊とするお寺に隣接している。村は物資の主要な集散地として位置している。地方でよく見かける藁葺き屋根の人家が何百軒も連なっているが、それに加えて大きな通りには小綺麗な瓦葺きの二階建ての建物があって、店と宿屋が軒を並べていた。また、この村には氏神様として太陽神である天照大神を祀っているとても美しい神社と、それに桑畑の中に蚕の神様を祀る小さな祠がある。
村の染物屋の内田という家には、明治七年生まれの太郎という少年がいる。彼が生まれたのは旧い太陰暦ではたまたま忌み日とされる八月七日であったため、信心深い昔気質の両親は恐れまた嘆いている。しかし暦が天皇の詔書で新たに太陽暦に改められる(a)と、その日は吉日であったので、同情していた村人たちはそら良かったじゃないかと慰めている。これらのことで両親の悩みも幾分なりとも和らげられはした。けれども、息子を氏神様へお参りに連れて行き、とても大きな提灯を奉納して、あらゆる災難から免れますようにと心より無病息災を祈願した。神主は祝詞を唱え、小さな坊主頭の上で御幣を振って御祓いをする。そして、子どもの首に掛けておきなさいと小さなお守りを授けた。両親は、また丘の上の観音寺にも参詣すると、そこでもお供え物をして、どうぞこの子にご加護がありますようにと仏様に祈った。
2
太郎が六歳になると、両親は村の外れに新しく建てられた小学校に太郎を入れた。太郎のおじいさんは筆を何本かと、紙や本それに石板を買ってやり、ある朝早くに太郎の手を引いて学校まで連れて行った。太郎は、石板などまるでたくさんの新しいおもちゃを貰ったようで嬉しかった。周りのみんなも学校はいっぱい遊べる楽しいところだと言ってくれたのでとても大喜びである。さらに、母は学校から帰ったらうんとお菓子をあげますよと約束してくれた。
学校――はガラス窓のある大きな二階建ての建物――に太郎とおじいさんが着くと、用務員さんがすぐに大きながらんとした部屋に案内してくれた。そこには厳めしい顔つきの男が机の前に座っている。おじいさんがこの男にお辞儀をして先生と呼びかけて、幼いこの子に優しく教えて下さるようにと丁寧に頼んだ。先生は立ち上がって会釈をすると、おじいさんに丁重に話しかけた。先生はまた太郎の頭に手を置いて、良く来たねと言った。けれども、太郎はすっかりおびえてしまった。おじいさんがじゃあねと言うと、ますます不安になってきて、いまにも家へ走って帰りたい気がする。しかし、校長先生が天井の高い、大きな白い部屋の講堂に連れて行くと、そこには長椅子に腰掛けたたくさんの男の子や女の子がいる。みんなが太郎の方を振り向くと互いにひそひそと囁いて、笑っている。太郎は自分が嗤われていると思うと、とても惨めに感じた。鐘の音が大きく鳴り響いた。すると演壇に立った校長先生が、静粛に!とピシャリと言ったが、それは太郎を怯えさせてしまった。先生が話を始めたが、なんだか話し方が親しめない感じがした。校長先生は学校は楽しいところですよなんて言わなかった。学校は遊びにくる所じゃなくて、一所懸命に勉強するところです。勉強は大変だが、辛かったり難しかったりしても勉強しなければいけませんと言い聞かせた。つぎにみんなが守るべき規則について説明して、守らなかったり怠けたりしたときの罰について話した。児童たちがみなシーンと静まると、今度は声色を変えて優しい父親のような感じで話し始めると――自分の子どものようにみんなを可愛がることを約束した。それから、校長先生は、みんなが賢い男や良き女になるようにという天皇陛下の御意向である布告(b)によってこの学校が作られたことを説明した。このため心より陛下を恭敬しかつ陛下に身命を捧げることがどんなに名誉なことかを訓話した。また校長先生はみんなが両親を敬うことや、それにあなたたち子どもを学校に通わせるために親がどれほど苦労しているかに触れて、それだから授業時間に怠けることがどんなに不正で恩知らずなことかについても教え諭した。そして子どもたちの名前を一人ずつ呼ぶと、これまで話したことについていろいろ尋ね始める。
太郎は、校長先生の話のうち、ほんの一部を聞いただけだった。彼の幼い心は、自分がこの部屋に入って来たときにみんなの視線を一斉に浴びて笑われたことでほとんど一杯だった。笑われたのが何であるかも分からず、とても傷ついていたので、他のことを考える余裕はなかった。それで自分の名前が呼ばれたときにはまったく何の心構えもしていなかった。
「内田たろう君、君は世の中で何が一番好きかね?」
太郎は起立すると、思った通りに「お菓子だよ」と答える。
するとみんながこちらを見て声をあげて笑っている。校長先生が咎めるような感じで尋ねた。
「内田たろう君、君は両親よりもお菓子が好きかね? 君は陛下への忠誠よりも菓子の方が好きか?」
それで、やっと太郎は自分が大きな間違いをしていることに気がついた。顔がとても火照ってきた。みんなが笑っている。たまらず彼は泣き出した。このことがまた笑いを誘った。先生が静かにと言って、同じような質問をつぎの児童にするまでみんなの笑い声がしていた。太郎は着物の袖で目を覆ってすすり泣いている。
鐘が鳴った。校長先生が子どもたちにつぎの時間は最初の書き方の勉強が他の先生からあるので受けなさいと伝えた。それまではしばらく遊んでいていいと言った。みんなは一斉に部屋の外に走り出てしばらく遊んでいる。みんなは校庭に出て行ってしまったが、太郎にはまったく気がつかない。太郎は自分がみんなの注目の的になっていたときに感じたことよりも、こうしてみんなから無視されていることの方に驚いた。先生を除けば誰からも一言も話しかけられなかった。今ではもう校長先生も自分の存在を忘れてしまったかのようである。彼は自分の小さな椅子にまた座った。そして泣きじゃくった。子どもたちが戻って来て自分を嗤うのではないかと恐れて、泣き声を押し殺しむせび泣いている。
突然に肩に手が置かれたのを感じてハッとした。すると優しい声がした。振り向くと、そこには今まで見たことのないようなとても温かい瞳があった――自分より一つばかり上級の愛らしい女の子がいた。
「どうしたの?」少女は穏やかに話しかけた。太郎はしばらくすすり泣いていた。やっとつぎのように答えた。
「こんな所に居たくないよう。ぼく、もうお家に帰りたい。」
「どうして?」彼の首にやさしく腕を廻しながら言った。
「みんな僕を嫌いなんだよ。だって誰も話しかけてくれないし、遊んでもくれないんだ。」
「そうじゃないわ!」「誰もあなたのこと嫌いな訳じゃないの。あなたのことをよく知らないだけよ。私だって、去年学校に初めて来たときはそうだったんだから。気にしちゃだめ。」
「だけど、みんな外で遊んでいるよ。僕だけここに残っているんだもの。」と太郎が不満そうに答えた。
「いいえ、違うの。あなたはそうじゃない。私と一緒においで、そして遊ぼうよ。遊んであげるから、さあ、おいで!」
太郎はまた大きな声をあげて嗚咽し始めた。太郎の小さな心は、自己憐憫や感謝の念それに新しく同情を得たことに気がついて、今度は喜びでいっぱいになった。それでほんとうに泣きたいのだった。泣けばなだめられて可愛がられるのはとても嬉しいことに違いなかった。
けれど、少女はにっこりとしているだけだった。太郎を急いで部屋から連れ出した。というのも、小さな母性本能がすべての状況を察したからだった。「泣きたいんだったら、泣けばいい。」「でも、遊ばなくちゃ、ね!」二人して一緒に遊んだのはなんと楽しかったことだろうか!
学校が終わると、家に連れて帰るためおじいさんが迎えに来た。太郎はまた涙ぐんだ。今度は彼の幼い遊び友だちとお別れしなければならなかったからだ。
おじいさんは笑って大きな声で言った。「なんだ、よし坊じゃないか――宮原のお芳だ! よしも一緒に帰ろう。家に寄ってけばいい。お芳もどうせ帰り道の途中だしなぁ。」
太郎の家で、遊び友だちと約束の菓子を一緒に食べた。お芳が校長先生の厳めしい口まねをして、いたずらっぽく訊いた。「内田太郎君、私より菓子の方が好きかね?」
3
宮原お芳の父親は、近くに水田を持っており、また村で店も営んでいる。彼女の母親は武家の出であったが、御一新の折りに武家制度が崩壊したときに、宮原家の養女となり、何人かの子どもを産んだが、お芳が一番下の子だった。この母親はお芳がまだ赤ん坊のときに亡くなった。宮原は中年過ぎていたが、後妻をもらった。それはある農家の娘で伊藤タマという名前であった。おタマは新しい銅のような褐色の肌をした娘で、目立つほどの美人で背も高く頑丈で働き者である。ただ、村人はこの縁談に驚いた。おタマは読み書きができなかったからだ。この驚きはついで興味を惹くことになった。家に入るや、彼女は絶対的な実権を手にした。おタマのことがもっと分かってくると、近所の者たちは亭主の宮原が尻に敷かれているのをあざ笑わなくなった。おタマは夫よりも商売のコツをよく心得ていたので、家の仕事をすべて切り盛りし、また夫の商売を取り仕切った。おかげで二年も経たないうちに宮原の稼ぎ高は倍ほどにもなっている。宮原は明らかに自分を金持ちにしてくれる、出来のいい女房をもらったと言える。また、おタマは自分の最初の男の子を生んだ後でも、継母として義理の娘には親切に振る舞っている。お芳はよく世話されて、みんなと同じように学校に入った。
子どもたちがまだ学校に通っている間に、長く待ち望まれ、また素晴らしい出来事が起こった。赤い髭を生やした見慣れない、背の高い男たち――西洋から来た外国人――が、たくさんの日本人の人夫を引き連れて、この谷にやって来て鉄道を建設したのである。それは村の後背地にある水田と森を越えて低い丘の縁に沿って敷設された。小さな駅舎が観音寺に続く古い道と交差する角の近くあたりに建てられた。村の名がプラットホームに設けられた白い駅名標に漢字で書かれている。その後に、電信柱が鉄道に並行して立てられた。そうしてやがて列車が入って来て甲高い汽笛を鳴らして停止してはまた発車する――それは古い墓地にある仏像をその石造りの蓮花の台座から揺するほどである。
子どもたちを不思議がらせたのは、北から南へと延びて鉄色に光る二本の線路が敷かれ、石炭殻が撒かれている見慣れない水平の道である。すると列車がさも荒れ狂ったドラゴンのようにゴーゴーと轟音を立てて叫んでは煙を吐き出し、またそれが通るたびに大地を揺らす汽車を見て驚いた。しかし、この驚きは好奇心になった――学校の先生の一人が、みんなに機関車がどういう作りになっているか黒板に書いて示した。また、電信の驚くべき仕組みを教えてくれたのでいっそう関心が増した。それに、新しい都と古都京都が鉄道と電信によって結ばれることを話してくれた(c)。その結果、二つの都の間を二日で旅することができるようになることや、一方から他方への通信もほんのわずか数秒で送ることができるなどの話をみんなで聞いた。
太郎とお芳は、とても仲の良い友だちになった。一緒に勉強したり遊んだりしたし、また互いの家を往き来した。けれどお芳が一一歳になったときに、学校を止めて、義母の手伝いをするように言われた。それ以来、太郎はお芳と滅多に会うこともなくなった。太郎も一四歳になって勉学を終えると、家の仕事の見習いをしはじめた。小さな弟が生まれると母は亡くなった。またその年には自分をはじめて学校に連れて行ってくれた祖父も他界した。これらのことがあって、太郎にはこの世は以前のようには輝かしいものとは思えなくなっている。一七歳になるまで彼の生活は変わらなかった。時々、宮原の家を尋ねては、お芳と話をした。彼女はすらりとした綺麗な女性へと成長している。けれど、太郎にとって彼女は今もなお昔のより幸福だった日々の楽しい遊び仲間であることに変わりはなかった。
4
春ののどかな陽気の日だったが、太郎はひどくもの寂しかった。こんなときにはお芳と会えたら愉しいだろうという思いが脳裏をよぎった。たぶん彼の記憶の中では、淋しさという一般的感情は初めて学校へ行った日のあの特別な経験と密接に結び付けられているのであろう。いずれにしても、彼の中の何か――たぶん死んだ母親の愛が作ったものか、あるいはおそらく他の死者に属している何か――が少しばかり愛情を欲したのである。そして、太郎はお芳からきっと愛情を得ることができるのではと思った。そこで彼は小さな店へと出かけた。店の近くまで来ると、お芳の笑い声が聞こえてとても甘美に響いている。そして、彼女は老農夫の客を応対していたが、このおやじさんもにこやかにまた饒舌にお喋りしている。太郎は待たなければならなかったし、お芳と話できるのを独り占めにできないのがじれったい。せめても彼女の傍にいることで、太郎はいくらか幸せな気分になった。じっとお芳を見つめているうちに、ふいに、どうして以前にはそんなに綺麗だと思わなかったのかと不思議に感じた。そう、お芳は本当に美しくなっている。村のどの娘よりもはるかに器量よしである。彼女を見つめながら、いつの間に彼女がこんなに可愛らしくなったのだろうかと思った。それを今まで気づかなかったのはとても迂闊なことであった。けれど、お芳は一心に見つめられていると思うと初めて羞じらわれる気持ちがして、小さな耳元まで赤く染めた。そして太郎は世の中の誰よりも見目麗しくて感じがとても良いと確信するに至ると、お芳にそんな気持ちをもう今すぐにでも告げたいという思いが募っている。いつまでも老農夫がお芳と話し込んでいるのでしまいには腹立たしくさえ思えてくる。数分の内に世界は太郎のためにまったく変化しているはずだったが、まだ彼は知る由もない。分かっているのは、この前会ったときと違ってお芳が神々しいようになったことである。やっと話す機会がめぐって来るとすぐに自分の恋しい胸の内を彼女に告白した。お芳もまた打ち明ける。それから二人は不思議に思った。というのは、自分たちの想いがほとんど同じであったからだ。だが、それは大きな災禍の始まりであった。
5
太郎がお芳と話しているのを見かけた老農夫は実は店に客として来ていたのではなかった。彼は実際の稼業の他に仲人や縁結びもしている。あの時は岡崎弥一郎という金持ちの問屋のためにそうしていた。岡崎はお芳を見かけたとき見初めて、この媒酌人に娘とその家族の身上や事情をできるだけ調べてほしいと頼んでいたのだった。
岡崎なる人物は、農民たちからもまた村の中の近所の者たちからもひどく嫌われていた。彼は、年も取って太った、また人相も悪くて声が大きい、横柄な態度の男であった。悪党だと言われている。彼は飢饉の折に米相場に投機して大儲けしたが、それは農民らにすれば決して許すことのできない犯罪行為であった。彼はこの県の生まれではなく、またここの農民と何らかの縁があるというのでもない。一八年前に、西国のある地方から妻と一人の子を連れてこの村へやって来たのである。彼の妻は二年前に死に、ただ一人の子も岡崎が虐待したので突然に家を出て行って、その行方は知れない。彼にはほかにも芳しくない話がいくつかある。一つは、生まれた西国の地方で、一揆の暴徒に襲撃されてその家と蔵とを打ち壊わされたので、命からがら逃げ出してきた。もう一つは、彼の婚礼の晩に、地蔵尊の饗応をするように強いられたというものである。
いくつかの地方では、あまり人望のない農夫の婚礼では花婿に地蔵尊の饗応をさせるという風習がある。屈強な若者たちの集団が道端や近隣の墓場から借りてきた石の地蔵を家の中に担ぎ込むと、その後をたくさんの群衆が付いて行く。座敷に地蔵を置くとたくさんの酒と御馳走を一度に要求するのである。もちろんこれは、それ自体大きなもてなしであり、拒めばたいへん危険なことになる。あらゆる招かざる客たちがもうこれ以上は飲み食いできないというまで饗応する必要がある。このようなもてなしをさせられること自体、公然の誅罰でありかつまた公然の辱めでもあった。
岡崎は老齢なのだが、若くて美しい妻を得たいと身の程知らずな望みを持っている。彼の富をもってしても、その望みを満足させるのは思ったほど容易ではなかった。何軒かの家が不可能な条件を持ち出して彼の申込みは断られていた。村長は、やや乱暴に、自分の娘を彼にやるくらいなら鬼にやる方がまだましだと言い捨てた。このような幾多の失敗の後で、この米問屋はおそらく他の地方で探すより他はないとあきらめかけていたが、たまたまお芳を見かけたのである。この娘をことのほか気に入っている。彼は、娘の家は貧しそうだから少しばかり金を渡せば娘を手に入れられると踏んでいる。そこで媒酌人を通じて宮原の家と交渉しようとしていたのである。
お芳の継母のおタマは農家の出で、まったく教育もなかったが、したたかな女である。彼女は義理の娘を決して愛しはしなかったが、利口だったので訳もなくお芳につらく当たるようなこともなかった。その上、お芳の方も、素直で優しい性格をしており、家にはとても役に立っている。しかし、お芳の美点を理解する同じ容赦ない抜け目なさは、この乙女の婚姻市場での価値を値踏みするのである。問屋の岡崎は狡猾さでは自分の上を行くような者とまさか取引することになるとは思ってもみなかった。おタマは岡崎の過去をかなりよく知っていた。また、その裕福さも知っている。また村の内外から妻を娶ろうとして画策してうまく行かなかったことも承知していた。彼女はお芳の美貌が老人の恋情を本当にかき立てているのではないかとも思っていたし、たいていの場合老人の恋には有利につけ込むことができることも判っている。お芳はとびきりの美人というほどではなかったが、あらゆる点で本当に可愛らしく、品のある娘である。岡崎が彼女ほどの娘を得ようとするなら遠方まで探し求めなければならないだろう。そのような娘を手に入れる特権のための支払を渋るのなら、おタマは他に気前がよく躊躇しない若い男たちを何人か知っている。岡崎にお芳をやるとしても、それはおいそれと簡単な条件では済まないはずであった。岡崎の最初の申込みを断ると彼は本性を露わしてくるに違いない。彼がほんとうに惚れているならば、この辺りの他の者ならば工面できないほどのかなりの結納金を要求したとしても用意するであろう。そのためには、彼のご執心の強さを確実に知ること、それに当分の間はこれらのことをお芳本人には黙っておくことがとても重要となる。媒酌人の評判は職業柄黙っておくことにあるから、そこから秘密が漏れる心配はなかった。
宮原家の方針はお芳の父親と継母との相談で決められている。父親はたいてい妻の計画に反対はしない。けれども、妻の方はまず夫を説得しようとした。まず、この結婚が多くの点で彼の娘の利益になると言う。結婚によって金銭的にも有利になると話した。本当は喜ばしくないリスクもあるけれども、相手の岡崎に一定の事前の解決に合意させておけば対処できると説いた。それから、おタマは夫にどう振る舞うべきかを教えた。この交渉の一方では、太郎がお芳を訪ねてくることは歓迎された。二人の互いの結びつきはたんなるクモの巣のようなものであり、必要とあらばすぐにでも取り払われるようなものにすぎないからである。岡崎がさもありなんという若い恋敵のことを聞きつければ、急いでこちらの思い通りの結論を出すだろう。
こんな理由から、太郎の父親がはじめて息子のためにお芳を嫁にと申入れたとき、この申込みが受け入れられも、また断りもされなかったのである。ただ、一つ出された反対は、お芳が太郎よりも一歳年上であるということだった。そんな縁組みは慣習に反している――これは本当のこと――というのである。けれども、この反対は弱いものだし、表向きさして重要でもない理由から選ばれたものであった。
同じ頃、岡崎からの最初の申込みは、その誠意がまず疑わしいという印象であしらわれた。宮原家は媒酌人の言うことに貸す耳をもたない。彼らはこの仲介人のもっとも分りやすい請合いすらてんで相手にしないという態度をとった。そこで岡崎は自ら魅力的な申し出だと考えるものを提案した方が得策だと気がついた。宮原の亭主は、この件は女房に任せているので、その決定に従う旨を約束した。
おタマは、いかにも軽蔑して驚いたというような表情をして、この申込みをすぐに断ることに決めている。彼女は面白くないことを言った。その昔、ある男が美しい花嫁をとても安く貰いたいと思っていた。やっと男は美しい女性を見つけると、女性は私は一日二粒の米しか食べませんと言った。それで結婚したが、やはり毎日、二粒の米を口にするだけだった。彼は幸せだった。しかし、ある晩、旅から帰って天窓からそっと覗くと、妻が驚くほど食べていた――飯と魚を山のように貪り食べており、また髪で隠れた頭の中の穴へあらん限りの食べものを詰め込んでいるのを見た。それで、男は自分が結婚した女が山姥だったことが分かった。
おタマは、先に断ったことの結果を一と月ばかり――じっと待った。欲しいと願ったものの価値は、それを手に入れることが難しくなればなるほど、いかに増大していくかをよく知っている。そして、彼女が予測したようについに再び媒酌人がやって来た。問屋の側は今度は以前よりも丁寧に対応する。最初の申込みに上積みして進んで魅力的な約束を提案してきている。これでおタマはすっかり岡崎を手中に収めることができると思った。おタマの作戦は複雑なものではないが、それは人間の性質の醜い面を本能的に知った上で立てられた計画である。彼女は自分の勝ちを確信した。約束は愚かな者のためにある。条件の付いた法的な契約は単純な者の落とし穴となる。岡崎はお芳を手に入れる前にその財産のうちの少なからざる部分を譲り渡すことになった。
6
太郎の父は息子がお芳と結婚することになればいいと心から願っている。そして、それを慣例のやり方で運んだのだが、宮原家からははっきりとした返事がないことに驚いた。彼は純朴で気取らない男である。しかも、同情という性質の直感も持っていたので、常日頃から嫌っているおタマのかなり慇懃無礼な態度からすると、望むようにはことは運ばないのではないかと訝しんだ。そこで、太郎には自分の心配をありのままに伝えた方がいいだろうと思って話したところ、太郎は落胆のあまり熱を出してしまった。しかし、おタマは計画の初めの段階では太郎を絶望させるような意図は持っていない。それで彼女は太郎の病気中には親切な見舞いの言葉の伝言とお芳の手紙を添えて送ったが、これは太郎の願望が再び蘇るという狙い通りの効果をもたらした。病気が直ると太郎は宮原家から丁寧に招かれて、お芳と店で話すことができた。けれど、太郎の父が先に訪ねてきたことにはちっとも触れられなかった。
恋人たちは氏神様の境内でしばしば会う機会があった。お芳は継母の小さな赤ん坊をおぶっていることもあった。他の子守りたちや子どもたちとそれに若い母親たちの群れの中で、彼らは妙な噂を立てられることもなく、いくつか言葉を交わすことができた。彼らの願いは一と月ばかり真剣には考慮されていない。そして、おタマは冷やかし半分に太郎の父に到底受け入れられないような金銭上の相談を持ちかけた。彼女は被っている仮面の端を少しつり上げて、本性を顕し始めている。というのは、岡崎はおタマが広げた網の中でさかんに藻掻いていたからである。その藻掻き様から見て、彼女は終わりがそう遠くないことを感じ取っている。お芳は自分の身辺で何が起こっているかなお知らなかったが、何かしら太郎の許へ嫁げないのではないかと案ぜられることがある。するとお芳は日一日と痩せ細り、顔色も次第に青白くなってきた。
太郎はある朝、お芳と話す機会があるかもしれないと思って弟を連れて神社の境内に行った。お芳と会って、自分はなんだか不安だと彼女に心のうちを明かす。というのは、幼い頃自分の母が首に掛けてくれた小さな木のお札が布袋の中で割れているのに気がついたからだ。
「それは縁起が悪い知らせじゃないわ」お芳が答える。「それは、貴い神様があなたを護ってくれた徴にすぎないのよ。村で病気があったとき、あなたは熱を出したけれど、もう元気になった。聖なる神様があなたをお守り下さったんだわ。だから割れたのよ。そう神主さんに言いなさい。もう一つ別のをくれるはずだから。」
彼らはとても不幸だった。しかし、別に誰に害を加えたということもなかったから、自ずと自分たちの前世や天道についての話になった。
太郎は言った。「たぶん前世で僕たちは互いに憎しみ合っていたんだ。おそらく僕が君に親切じゃなかったか、君が僕にはそうだったからだよ。だから、これは僕たちへの罰なんだ。お坊さんはきっとそう言うさ。」
お芳は少し冗談めかして答える。「私はそのとき男だったのよ。あなたは女で。私はあなたを好きで好きでたまらなかったんだけど、あなたは私にまったく気がなかった。私はそれをよく覚えているわ。」
太郎は、すまなさそうに微笑みながら「君は菩薩じゃないよ。」と返答した。「だから君は何にも覚えていることなんてできないんだよ。僕たちが覚えているのは菩薩道の十階のうちの最初の階においてだけらしいんだ。」
「どうして分かるの? 私が菩薩じゃないって?」
「君は女だからさ。女は菩薩にはなれないんだ。」
「観音菩薩は女性ではないの?」
「そうだね。それはそうだ。でも菩薩はお経のほかは愛することができないんだよ。」
「お釈迦様には奥さんや子どももいたでしょう? お釈迦様は妻や子を愛さなかったの?」
「そうじゃないけど。でもお釈迦様は妻や子を捨てなければならなかったんだって、知ってるよね。」
「それはとてもいけないことだわ。たといお釈迦様が行われたことだとしても。私、この話、全部は信じない。あなた、私を奥さんにしたら、私を捨てる?」
二人はこんな風に教えや道理を言い合っては議論し、ときおりは笑い合った。二人一緒にいられることが何よりも愉しかったのである。けれども、お芳は急にまじめになると話し始めた。
「ねえ、聞いてよ。私、昨夜夢を見たの。どこか分からない川とそれに海を見た。川の側に私が立っているような気がした。その川は海に注いでいる。私、とても怖かった。ほんとに怖かったんだけど、なぜだかは分からなかった。見てみると、川にも海にもぜんぜん水がないことに気がついたの。けれど、仏様の骨だけがあって、それが全部動いているの。ちょうど水のようによ。」
「そしたら、今度は私は家にいるような気がしたわ。そして、あなたが私に着物を作るようにとくれた綺麗な反物を仕立てて、私がそれを着てみたの。そしたら、なんだか不思議な気がしたの。だって、まずそれにはいろんな色の模様があったはずだと思っていたけど、いつの間にやら白無垢の着物になっていたの。そして、私はなんと死んだ人の着物のように左前にして着ていたんだわ。それから、私は親類の家をみんな訪ねて行って、お別れをするの。私、冥土に行きますとみんなに言ったわ。みんなはどうしたのと尋ねたけれど、答えられなかった。」
「それはいいよ」と太郎が言った。「死者の夢を見るのはきっと縁起がいいんだ。たぶん、それは僕たちが夫婦になるという徴だよ。」
こんどは乙女は答えなかったし、微笑みもしなかった。
太郎はしばらく黙っていたが、それから付け加えた。「もし、君がよい夢じゃないと思うんだったら、よし、庭の南天の木にそれを囁いておこう。そしたら、それは真実とはならないからね。」
その日の夕刻、太郎の父は宮原のお芳が岡崎弥一郎の嫁になるという知らせを受けた。
7
おタマは実に頭のよい女である。大したミスもしなかった。彼女は、自分より劣っている者たちを搾取して楽々と人生に成功していける小利口な人間である。彼女の先祖代々の農民としてのあらゆる経験は、忍耐心、ずる賢さ、巧みな知覚、それに機敏な先見の明や吝嗇ともいえる倹約精神などに見られるが、彼女の無学文盲な頭脳の中に完璧な機械として凝縮されているのである。この機械は、それを生み出した環境において、また、それがうまく捌くことのできる特定の人間――つまり農民という種類――の材料に対してであれば、申し分なく働くのである。だが、おタマがよく理解できない別の種類の人たちが存在しているのである。なぜというに、おタマにはそれを解明できるような先祖代々の経験を少しも持ち合わせていなかったからである。彼女はサムライと平民とは別の種族であるという伝統的な考えをけっして信じようとはしなかった。法と慣習とが確立したような差異を除けば、この士族階級と農民階級との間には何らの区別も存在しないと考えていたし、またこれらそのものが悪であると思っている。彼女の考えによれば、法と慣習のために旧士族階級のあらゆる人々は多かれ少なかれ無力や愚かな者にされる結果となったのである。こうして密かに士族階級を軽蔑していた。彼らが一所懸命に働かないことや商売のやり方についてまったく無知であったために、士族が富裕層から貧困層へと没落するのを見てきた。新政府が華士族らに交付した金禄公債証書(一八七六年)の金が華士族の手からもっとも下層な商人階級であるずる賢い投機家連中の手中に落ちるのを見た。おタマは弱さを軽蔑した。無能さを馬鹿にした。かつて家老が通るたびに草履を脱ぎ捨て、地面に頭をこすりつけねばならなかった者たちから、今度は援助を乞わなければならなくなった元家老よりも、ごくありふれた野菜売りの方がより優れた存在だとおタマは評価している。お芳が武家出の母親を持っていたことも別に有利なものとは考えていない。おタマはお芳の高貴さを武家出の母親の出自に由来するものと見たが、その出自こそが不運であると思っている。彼女は、お芳の性格の中に上位の身分ではない農民の眼から読み込みうるすべてのものを読み込んでいた。なかでも、この娘につらく当たっても何も得られないことである。お芳に見られる性質は彼女が嫌いなものではない。しかし、お芳にはおタマが決してできない別の性質――つまり道徳的な悪に対する深くまたよく配慮された感覚、きっぱりとした自尊心それに肉体的苦痛に打ち勝つことのできる肝の据わった意思力などがある。このようにして、岡崎に嫁ぐよう告げられると、お芳がきっと抵抗するに違いないと思っていたおタマは騙された格好であった。彼女は計算違いをしたのである。
最初、その少女は死んだかのように蒼白になった。しかし、しばらくするとお芳は顔を赤らめ、微笑んでお辞儀をし、また、孝行娘らしく改まった言葉で万事両親のご意思に従い申しますと返答したので、宮原の両親も思いもよらず驚いた。彼女の態度には内心不満そうな様子も見られない。おタマは非常に喜んだのでお芳に打ち明けた。縁談交渉の中でのいくつかの笑い話や岡崎がどんなに多くの犠牲を払うことになったかについて話して聞かせた。さらに、本人の同意なしに老人の元へ嫁ぐことに決まったうら若い婚約者に掛けられるようなありふれた慰めの言葉に加えて、おタマは岡崎を思い通りに操る方法についてもお芳にいくつかの貴重なアドバイスもした。太郎の名前はついぞ一度も出なかった。継母の忠告に対して、お芳は優雅に手をつき平伏してお辞儀をして、従順に礼を述べた。それは確かに貴重なアドバイスである。おタマのような先生に十分に教えられた優秀な農家の娘ならば、岡崎との生活をうまくやり遂げていくことはできるだろう。けれども、お芳は農家の血を半分だけ引いているにすぎない。自分の将来がどんなものであるか宣告された直後に、お芳が突然に最初は蒼白となり、その後に紅潮したのは、おタマがその性質を感じ取ることができなかった二つの感情によって引き起こされているのである。両方とも、それはおタマの計算高い経験においてなされたものよりもはるかに複雑で素早い思考を示していた。
最初は恐怖によるショックのためである。それは、継母にまったく道徳的感覚のなさや逆らってもほとんど望みがないこと、ただ単に必要でもない金銭的な欲に駆られた動機のためにぞっとするような老人に実質自分を売り渡すこと、そしてこの取引の酷さと恥知らずさを心底から感じ取ったことに伴うものだった。しかし、それと同時に、お芳は、最悪なものに立ち向かう勇気と強さ、それに狡猾さに対抗する英知が必要なことをすっかり認識したのだった。そのときお芳は微笑みを浮かべた。微笑みながら彼女の若い意思は鉄のようになった。それは揺るぎない鋼鉄のごとき堅固な意思である。自分がただちに何をなすべきかを正確に悟った――彼女に流れるサムライの血がそれを教えたのである。他方で時を待って機会を得ようと考えた。そして、お芳は勝利は自分にあると強く実感していたので、思わず声に出して笑いそうになるのをこらえなければならなかった。おタマの方はお芳の瞳のこの輝きを見て、お芳が満足した感情を示したのだろうとすっかり信じ込まされたのである。金持ちとの結婚によって実際いろいろ利益になることににわかに気づいたからだろうと思ったのであった。
今日は九月一五日である。そして婚礼の日取りは一〇月六日と定まった。それから三日の後、おタマは夜明け前に起きたが、すでに継娘が夜中に居なくなっていることに気づいた。内田太郎も前日の午後以来父が見かけることはなかった。その後、二・三時間ばかり経って二人からの手紙が届いた。
8
早朝に京都からの一番列車が入って来た。小さな駅は急ぐ人と音で満ちあふれている――下駄のカランコロンという音、話し声それに菓子と弁当を売る少年の途切れ途切れの呼び声、「菓子はいかがですか――」「寿司はよろしいか――」「弁当いかが――!」 五分も過ぎると、下駄の響きも止み、列車のドアもバタンと閉じられた。物売りの少年たちの甲高い声も止んだ。笛が鳴り、列車がガタンゴトンと動き始める。それはゴトゴトと音を立て、白い蒸気を吹き出すとゆっくりと北へ向かって走りだした。小さな駅にはすっかり誰もいなくなった。改札口のドアを閉めると、巡査は静かな水田地帯を眺めながらプラットホームをこちらから向こうへとゆっくりと歩き始めた。
秋になった――「強い光の時」だ。俄然太陽の光は白くなり、影はシャープになる。あらゆるものの輪郭は割れたガラスの切れ口のようにはっきりとしている。苔は夏の暑さのために乾いてしばらく見えなかったが、火山灰の黒土が露出した日陰の場所では光沢のある柔らかな緑色の部分や固まりとなって息を吹き返してきている。松林からはツクツクボウシの甲高い鳴き声が聞こえている。水路や溝の上には小さな静かな光の輝き――エメラルド色や薔薇色そして鉄の淡青色に煌めき、音もなくジグザグに飛び交って――トンボがあちこちに止まっている。
朝の空気がとても綺麗に澄み切っていたので、巡査は北の方の線路の遙か向こうに、何かにはっと気づいて手をかざしてよく見ようとした。それから時計に目をやった。しかし、日本の警察官の黒い眼は、大概狙いを定めた鳶の目のように、その全視野の中にわずかでも変わった事があるとすぐに気づくのである。それで思い出したことがある。遠方の隠岐島という所で、かつて私自身が、旅館の前で行われていた目隠しの踊りをそっと見たいと思って、二階の障子に小さな穴を開けて踊りを眺めていた。白い制服と帽子の警官が通りを歩いてきたが、そのときはまだ夏の盛りである。彼は踊りや群衆を見ているようには思えなかった。自分の頭をあちこち見渡さずに歩いていたからだ。それから、彼はやおら立ち停まると、障子に開けた穴をじっと見据えている。その穴には、瞬時にその形から外国人の眼が覗いていると判断したのだった。そして、旅館に入ってくると、私に旅券の提示を求めたが、それはすでに先ほど彼が検査したものだった。
村の駅で巡査が見たものは、そして後日の報告によると駅の北方八〇〇メートルばかりの地点で二人の者が、明らかに村の北にある農家から水田地帯を横切って踏切に近づいてきた。うちの一人は、その着物や帯からして、とても若い女性だろうと思われた。東京発の早朝の急行列車が数分後には到着するはずである。その勢いのよい煙は、駅のホームからも望むことができる。二人の姿は汽車が接近している線路に沿って急いで走り出した。カーブを曲がったところで二つの人影は見えなくなった。
この二人とは太郎とお芳である。彼らが急いで走っていたのは、巡査の目を避けるためとできるだけ駅から離れた遠くで汽車を待ち受けるためである。カーブを通り過ぎたところで、二人は走るのを止めて歩いた。というのは、煙がこちらへやって来るのを見たからである。二人は汽車が見えると、すぐに線路から離れた。それは機関手を驚かしてはいけないと思ったからだ。そして、互いに手に手を取り合って待っていた。つぎの瞬間を待って、低い轟音が聞こえたときに、今だ!と二人は思った。再び線路に戻ると、互いに振り向き、腕を互いに廻してひしと抱き合う。頬と頬とを寄せ合って、そっとまた急いでレールの上に二人は横たわった。レールはすでに全速力で接近してくる汽車の振動で金床のように唸っている。
若者は微笑んだ。乙女は彼の首にしっかり腕を巻き付けて、耳元に囁いた。
「来世もまた来来世も、わたしはあなたの妻、あなたは私の夫よ、太郎さま。」
太郎に応える暇はなかった。というのは、空気圧式ブレーキの装置もなく速度の出た汽車を一〇〇メートルもない距離で緊急停止させようとした、つぎの刹那、鉄輪は二人の上を大きく空を切って回った。――ちょうど巨大な裁断機のように(d)。
9
村人たちは二人が一緒に葬られた比翼塚に竹筒に入れた花を供えていた。線香を焚き、念仏を唱えた。これは通常ではあり得ないことである。というのは、仏教では情死は禁じられており、この墓地は仏教徒たちのものであるからである。しかし、そこには宗教があった――深い敬慕という信仰が。
どうして人々がこのような死者に祈るのかと聞かれるだろう。すべての者が二人に祈るというわけではないが、それでも恋人たちは祈ったし、とくに不幸な恋をしている者たちはそうするのである。他の人たちは墓地を飾ったり、また敬虔な祈りの言葉を捧げている。とりわけ恋人たちは同情と救いを求めて祈るのである。私もなぜだろうかと自問せざるを得なかったが、つぎのような単純な答えを得た。死んだ二人がたくさん苦しまなければならなかったからだと。
このような祈りを促している観念は仏教よりももはるかに古くて、同時にもっとも現代的でもある――「苦しみという永遠の宗教の観念」といえよう。