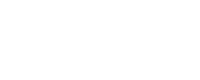そうはちぼんとは、石川県に伝わる怪火(かいか)である。ほかの呼び方では、ちゅうはちぼんというのがあるな。
名前の本来の意味は仏具であり、シンバルのような楕円形の形をした楽器妙八(みょうばち)のことであり、怪火の姿がこの楽器に似ていることが由来とされる。
シンバルを2枚合わせた形を想像してみい。これを90度横に回したら、まさにUFOの形になるんですな。
そうはちぼんは、秋の夜、羽咋市(はくい)にある眉丈山(びじょうざん)の中腹を東から西に、不気味な光を放ちながら群れて移動する。鳥屋町(とりやまち)羽坂(はざか)の六所の宮から一ノ宮の六万坊(ろくまんぼう)へ移動するとも云われている。正覚院(しょうかくいん)に伝わる『気多古縁起』(けたこえんぎ)によれば神通力を用いて自由自在に空中を浮遊する光の玉であるとの記述が見られ、「江戸時代に現れたUFOのことではないだろうか」などとの意見もあるんですな。
UFOの町として名高い石川県羽咋市では『そうはちぼん伝説』が各地に伝承されており、その特徴などからUFOと絡めて扱う書物が多いためか、そうはちぼんは他の一般的な怪火、鬼火などとは異なった捉えられ方をしている。
また眉丈山周辺では、「ナベが空から降ってきて人をさらってゆく。」という神隠し伝承も残っているという。
これもなかなか面白い逸話ですな。まさに土鍋はUFOそのものです。
では、ここでひとつ石川県に伝わっているお話をひとつ。
前述の説明と重複しますが、どうぞ一席お付き合いください。
秋の日暮れていつのまにか夜となる時期に、西山、これは眉丈山のことですな。この山の中腹を東より徐々に西に移り行く怪火を「そうはちぼん」、あるいは「ちゅうはちぼん」という。
そうはちぼんは、(旧鳥屋町・現中能登町)羽坂(はざか)の六所の宮より現れて、羽咋市の一の宮の六万坊へと移動する怪火である。
かつて、そうはちぼんが、一の宮権現(気多大社)に、人を食いたいと願ったところ、鶏の鳴かぬうちに此処まで来れば、人を食わせてやろうとの一の宮権現から言われた。
そこで、そうはちぼんは、毎夜日暮れ頃となると、一の宮へ行き人を食おうと、羽坂から現れるのだが、良川(よしかわ)を過ぎる頃には、八ッ時、丑の刻、午前2時頃ですな。金丸(かねまる)あたりまでくるとまごつきだし、柳田(やなぎだ)あたりまで来たときには、鶏の鳴き声を聞くこととなり、仕方なく夜のうちに六所の宮に引き返すといわれている。よってこの鶏の鳴き声は、一の宮権現が鳴かせているのだと言われているんですな。
昔、大正時代の頃、(能登部の眉丈山を挟んで裏側にある)後山の西照寺の住職が、夜中寺に帰ろうとして、眉丈山の中腹にかかったところ、あたりがポッと明るくなったので、不思議に思ってあたりを見回すと、大きい高張提灯とおぼしきものが現れ、山の背より谷に真一文字に緩々(ゆるゆる)と進んでいった、という話も残っている。
ちなみに石動山続きの山にも、七尾の古府の城山の首塚あたりから現れる怪火もあるといわれている。
以上、妖怪とUFOが融合した、とても興味深いお噺でございます。